原さんが刺激を受けたという「対話」の作法は、イギリスではどのように習得されるものなのでしょうか。教室での対話や議論は、先生によって促されて始まるものとはいえ、テストされるわけでも成績表になるわけでもありません。それなのに、クラスメートがみな自分の意見を述べ合うという状況が生まれるのはなぜか。その疑問に原さんは次のように答えてくれました。
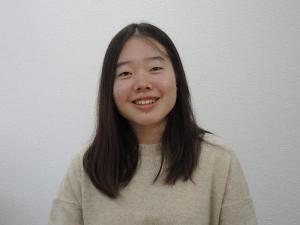
議論を進めるうちに論点についての当事者意識が芽生えてくることが経験的に分かっているのかもしれません。すべての科目が生活に関わっているというか、学業が市民育成ということと結びついているように思います。一見自分に関係のないように感じられることについても、考える努力を続けるように教育されているような印象を持ちました。私のいた学校ではクラスの人数が15名から20名ということもあって、自然と議論が濃密になっていたのを思い出します。
学びがテストのためとか受験のためということではなく、自分たちの日常に関係しているという意識が推進力になっているということを説明してくれた後、原さんはケンブリッジの面接対策を高校で受けていたときに、自分の知らないトピックにどう対応するかという練習を受けていたことも話してくれました。
私がケンブリッジで目指していたのは、法学や経済学が関係している学部だったので、受験学部の内容に関するトピックについてはあらかじめ準備をして対話の練習をすることもありました。例えば法学であれば、ある刑事事件の概要を与えられてから対話を始めるとか、経済学であれば、鉄道を国有化するべきかどうかといったトピックを与えられて対話するといったことです。ですが、学校の先生が強調していたのはむしろ、自分の知らない初見のトピックについてどう対応するかということでした。「分からない」とか「知らない」という答えで終わらせるのではなく、相手のいろいろな考えに対応して、自分の意見を発展させていく方法を学びました。相手の主張に応じて自分の意見を途中で変えることもあれば、あえて変えずに対立する立場を維持したりなど、相手とともに思考を発展させていく状態を生み出すよう努力しました。
話を聞いてなるほどと合点がいきました。というのも、この態度こそいわゆる "open-mindedness" の意味するところだと了解されたからです。バートランドラッセルがクリティカルシンキングの前提として "open‐mindedness" を想定したように、"open-mindedness" は「心」というよりはむしろ「理性」に関して開かれた態度なのでしょう。自分の持っているバイアスを取り外すような機能を果たすわけです。
原さんの話はさらに「fallacy(誤謬)」へと及んでいきました。例えば、人格攻撃をしないとか論点のすり替えを指摘できるとか、相関関係と因果関係を取り違えないといった議論のルールですが、こういうことは、言語化以前にみなそういう感覚を持っていると話します。そのような技法というよりむしろ社会の多様性が対話や議論の根底にあることが関係しているのではないかと指摘します。(続く)




