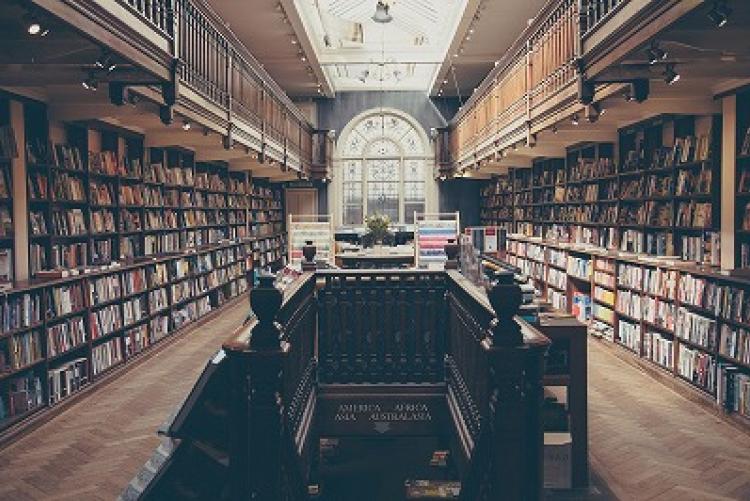序文:未来への不安から、未来への期待へ
予測不能な時代において、どの学校を選ぶべきか。多くの保護者や生徒が抱えるこの不安に対し、サレジアン国際学園は明確な答えを提示しています。同校は単に変化に適応するのではなく、「第2ステージ」へと移行し、教育の新たなパラダイムを積極的に設計しています。本記事では、同校のGWEご登壇から明らかになった、教育の常識を覆す5つの驚くべき挑戦を紐解き、未来の教育の一端を明らかにします。
--------------------------------------------------------------------------------
1. 「まず思考、次に知識」―学びの順番を逆転させるPBL型教育
サレジアン国際学園は、従来の「積み上げ型」学習モデルから根本的に脱却しようとしています。これまでの教育が「基礎知識→応用力→思考力」という順番であったのに対し、同校は「思考力」からスタートする新たなモデルを導入。これは特定の探究授業だけでなく、全教科にわたりプロジェクト・ベースド・ラーニング(PBL)として実践されています。
このアプローチがなぜ革新的なのか。それは、学校の存在意義そのものを問い直しているからです。宗像校長は、「得点力を上げる学びは、予備校や学習塾、あるいはAIでもできる」と指摘します。しかし、学校でしかできないことがある。それは、多様な仲間と協働し、未知の課題に対する最適解を導き出す「総合知」を育むことです。生徒が自ら思考する中で課題解決のツールとして知識を獲得した場合、その知識は深く定着します。この学び方は、学校を単なる知識伝達の場から、本質的な知的好奇心を高める場へと昇華させる挑戦なのです。
「人から与えられた知識っていうのはやっぱり忘れちゃうんですよね...学校っていうのは学校生活を通じてやっぱり知的好奇心を高める場だと思っているんです。」と語ります。
--------------------------------------------------------------------------------
2. 「カトリックは宗教ではなく哲学」―世界市民を育むための共通言語
同校は、そのカトリックというアイデンティティを、単なる「宗教」としてではなく、「哲学」であり「思想」であると再定義しています。このユニークな捉え方は、教育の根幹をなす重要な要素です。
この再定義により、生徒たちは変化の激しい時代においても決して揺らぐことのない道徳的な指針、いわば「背骨」を持つことができます。さらに重要なのは、この哲学が、言語の壁だけでなく「価値観の壁」をも超えるための「共通言語」として機能する点です。世界人口の多くが共有するこの思想体系を理解することなくしては、「本当の世界市民」とは言えない、と同校は考えています。宗像校長自身がカトリック信者ではないという事実が、この開かれた哲学的アプローチを象徴しており、真の世界市民を育成するための強固な基盤となっています。
--------------------------------------------------------------------------------
3. コース間の壁が消える?―学校全体がバイリンガル環境へ
サレジアン国際学園では、本科コースとインターナショナルコースの垣根が意図的に取り払われ、学校全体がひとつの学習共同体として機能し始めています。
• 本科: 毎週8時間の英語授業のうち、6時間をネイティブの「インターナショナルティーチャー(IT)」が担当します。
• インターナショナル・スタンダード (SG): 英語で行う授業が週12コマから20コマへ大幅に増加。新たに数学と社会も英語で学ぶようになります。
• ハイブリッドクラス (Hybrid Class): 異なるコースの生徒が同じホームルームで共に学び、日常的に助け合い、協力し合う環境が生まれています。
この構造は、「国内向け」と「国際向け」という単純な二元論を超越し、すべての生徒にとって英語が特別な「教科」ではなく、日常的に思考し、対話するためのツールとなることを目指しています。まさに同校が掲げる「英語は日常だ」という思想の具現化です。
--------------------------------------------------------------------------------
4. 「世界標準」を目指す―海外から学ぶだけでなく、海外と対等に学び合う
同校が目指すのは、単に海外で通用する人材ではなく、世界と対等に渡り合える「世界市民」の育成です。その具体的なステップとして、デュアルディプロマ・プログラムであるWACE(西オーストラリア州の高校卒業資格)を導入。これにより、生徒は世界の大学に直接出願することが可能となり、多くの場合、現地の大学進学準備コースをスキップできます。
この背景には、「日本の生徒が海外から一方的に学ぶ」のではなく、「世界と対等な立場で学び合う」というマインドセットの転換があります。説明会では、言語の壁さえ乗り越えれば、日本の生徒は海外の統一テストで「圧倒的に点数が高い」という事実が示されました。このポテンシャルを解放することで、サレジアン国際学園は、世界97カ国に広がる姉妹校から教育イノベーションを「学ばれる」存在、つまり教育の潮流を逆転させるモデル校になることを目指しているのです。
--------------------------------------------------------------------------------
5. 新たな挑戦「メディコ」―未来の理系リーダーを育成する専門プログラム
本科コース内には、新たに革新的な専門プログラム「メディコプロジェクト(MEDICO Project)」が設立されます。
このプログラムは、医学、工学、情報科学といった分野に強い関心を持つ生徒を対象としています。大学レベルの発展的なトピックを扱い、外部の研究機関とも連携。博士号を持つ教員を含む、高度な専門知識を持つ指導陣が、未来のトップレベルのSTEM人材を育成します。このプログラムは、単なる知識の暗記から脱却し、最も要求の厳しい科学分野で創造者・問題解決者となるための高度な専門ツールを生徒に提供するという、同校の教育理念を体現しています。
--------------------------------------------------------------------------------
結論:未来の教育は、偏差値や実績だけで選ぶ時代ではない
思考力から始めるPBL、グローバルな共通言語としての哲学、学校全体を覆うバイリンガル環境、そして世界と対等に学び合うマインドセット。サレジアン国際学園の挑戦は、個別の改革ではなく、未来の「世界市民」を育むために緻密に設計された、相互に連携する一つの戦略です。同校が伝えるメッセージは明確です。偏差値や合格実績といった目に見える指標だけでなく、その学校が子供の「見えない能力を引き出し」、本質的な「成長力」を育む環境であるかどうかで選ぶべきだということです。
2036年に活躍する子供を育てるために本当に必要なことは何でしょうか?それは、用意された答えを覚えることではなく、自ら正しい問いを立てる力を養うことなのかもしれません。