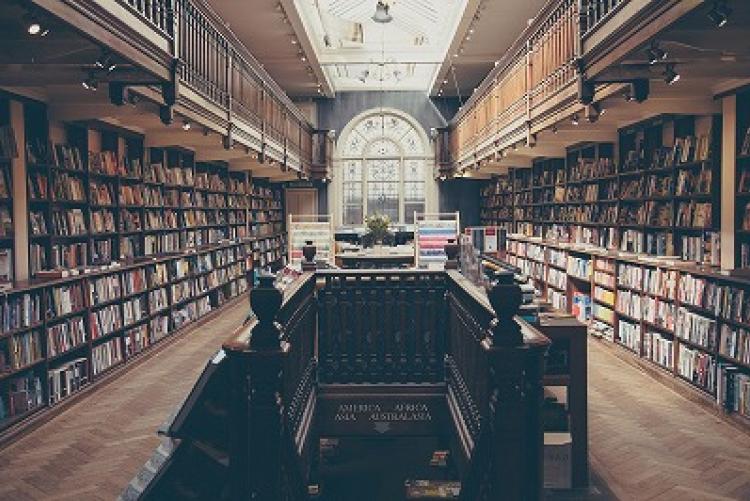日本の世界幸福度ランキングがG7で最下位に近い50位台に留まっているのはなぜか。その大きな要因の一つに、調査項目である「自分の人生を自分で選択できるか」という問いに対し、日本の若者の多くが「いいえ」と答えている現実があります。偏差値という画一的な物差しで評価され、常に他人との比較の中に置かれる教育環境が、生徒たちから主体的に生きる自信を奪っているのかもしれません。
この根深い課題に対し、独自の哲学で「豊かな人生を歩める人」の育成を目指すのが田園調布学園です。同学園が教育の根幹に据えるのは、「自分の人生を生きる」というテーマ。そして、その思想を支えるのが「捨我精進(しゃがしょうじん)」という建学の精神です。これは「今の自分を超える」ことを意味し、他人との比較ではなく、過去の自分を乗り越えていくことに成長の本質を置いています。
このブログでは、田園調布学園が実践する「捨我精進」の哲学に基づいた、常識を覆す5つの驚くべき取り組みを解き明かしていきます。
1. 評価の軸は「他人との比較」ではなく「過去の自分」。偏差値から解放する「ルーブリック」
日本の教育を支配する「偏差値文化」への直接的な対抗策として、田園調布学園が導入しているのが「学校ルーブリック」です。中学受験を経て入学する生徒たちは、どうしても偏差値という数字で自分の価値を測る思考に陥りがちです。同学園は、まずその呪縛から生徒を解放することを教育の出発点とします。
ルーブリックとは、学園が目指す人間像を具体的な能力として示した評価指標です。生徒たちはこれを用いることで、「半年前や1年前の自分と比べてどう成長したのか」を客観的に可視化し、自己評価を行います。この内省的なプロセスは、単なる抽象論ではありません。中学の3年間で必修とする問題解決の思考法「デザイン思考」といった具体的な方法論によって支えられています。
なぜこの仕組みを重視するのか。清水豊校長は、その思想を次のように語ります。
やっぱり自分の評価って他人との比較だけではなくて、この ルーブリック表を見ながら、今の自分が例えば 半年前や1 年前の自分とどう成長したのか、これを見ながら自分で考える、ま、そういう風になって欲しいっていう話をしてるんです 。
他人という外部の物差しではなく、自分自身の成長という内部の物差しを持つこと。これこそが「捨我精進」の第一歩であり、生徒が他人の評価に惑わされず「自分の人生を選択する」ための自己肯定感を育む、戦略的な介入なのです。
2. 女子校なのに理系が約半数。「本物の興味」を生むジェンダーバイアスなき環境
田園調布学園における驚くべき事実の一つに、理系を選択する生徒の割合の高さが挙げられます。その割合は毎年約45%、多い年では半数を超えます。これは、一般的な女子校のイメージとは大きく異なる、非常に高い数字です。
しかし、学校側が意図的に理系進学を推奨しているわけではありません。この背景には、教育現場における緻密な戦略があります。特に中学段階の数学や理科の教員が、パズルや実験などを多用し、学問そのものの面白さを徹底的に伝えることに注力しているのです。清水校長が「根拠はない」と指摘するように、「女子は文系、男子は理系」といった社会に根付く無意識のジェンダーバイアスから解放された環境で、生徒たちは純粋に自分の知的好奇心と向き合います。
この環境で育った生徒の価値観を象徴する、ある卒業生のエピソードがあります。
ある国立の難関大学に行った子が「女の子なのにすごいね」って大学生になった時言われたとか...で自分はすごいと思ったこと1度もないって言うんですよ。中高時代に。
社会的バイアスがいかに無意識のうちに人の可能性を狭めているか。同校の環境は、生徒が周囲の雑音に惑わされることなく、自分自身が「本当にやりたいこと」を発見し、それを堂々と選択する力を与えているのです。
3. 目指すは「グローバル人材」ではない。「どこでも生きていける」ための土台=「自分の軸」
教育界で頻繁に使われる「グローバル教育」という言葉を、清水校長は安易に用いません。同学園が目指すのは、その本質である「どこでも生きていける力を育てること」だからです。
海外で活躍するために必要なのは、英語力以前に、その土台となる「自分の軸を作ること」だと校長は強調します。そのために重視するのが、「なぜ?どうして?」と物事の本質を問い続ける姿勢です。校長は、アメリカの子供たちが頻繁に“because”という言葉を使い、自分の考えの理由を説明する文化を引き合いに出し、論理的に思考を言語化する力の重要性を説きます。
この哲学は、アジア諸国との交流プログラムに色濃く反映されています。特にフィリピンでの研修では、生徒たちが自分たちでおにぎりを作り、スラム街の食事もままならない子供たちに提供するという体験をします。このような活動は、自分を客観視させ、「自分とは何者か」という問いを突きつけます。また、プログラムをアジアに重点を置く理由も明確です。「近隣のアジアの国の人たちと対等に交流できる」日本人を育てるという、明確なビジョンがあるからです。
流行りの言葉に流されず、教育の「本質」を追求する。強固な「自分の軸」を築くことこそ、どんな環境でも自分の人生を主体的に選択できる、真の国際人を育てることに繋がるのです。
4. 「数学×歴史」「音楽×数学」。学問の壁を取り払う「教科横断型授業」の面白さ
多くの学校では、文系・理系に分かれると、選ばなかった教科への興味が薄れがちです。この学問の分断という課題に対し、田園調布学園は「教科横断型授業」という戦略的介入を年間約40講座も実施しています。
• 歴史×数学: 江戸時代の「家紋」を、当時使われていた「竹のコンパス」などを使いながら、数学で習う「作図」の知識で描いてみる。
• 国語×美術: レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」に関する評論を読解した後、美術の視点から絵を分析し、生徒自らが登場人物のポーズをとって心情を考察する。
• 音楽×数学: モーツァルトが用いた「サイコロ遊び」で作曲を体験し、その仕組みを数学の「確率」の視点から分析する。
これらの授業の狙いは、単に知的好奇心を刺激するだけではありません。探究の授業で学んだ「デザイン思考」を、他の教科や活動でも応用する「思考の横断」を促すことにもあります。知識を断片ではなく豊かな繋がりとして捉える視点は、複雑な社会問題を解決し、自らの未来を選択する上で不可欠な、複眼的な思考力を養います。
5. 土曜日は「授業」をしない。170講座から自由に選ぶ「土曜プログラム」で本物の探究へ
田園調布学園の土曜日の使い方は、その教育哲学を最も象徴しているかもしれません。年間約15回ある登校土曜日のうち、8回は通常の授業を行わず、すべて「土曜プログラム」に充てられています。
芸術、科学、語学、フィールドワークなど、外部の専門家を講師に招いた170もの多様な講座が開かれ、生徒は学年の垣根を越えて、自分の興味だけで完全に自由に講座を組み合わせます。イタリア語の隣でプログラミングを学び、その向こうでは多摩川でフィールドワークが行われる。これが日常の光景です。
このプログラムの目的は、多様な体験を通じて自分の興味を広げること、そして時には「これは思っていたのと違った」と知る機会を与えることにあります。これこそが、「自分の人生を自分で選択する」ための、最も実践的な訓練です。6年間、自ら「選ぶ」という小さな成功と失敗を繰り返すことで、生徒たちは人生の大きな選択に臆することのない、しなやかな自己を発見していくのです。
結び
これまで見てきた5つの取り組みは、すべて「捨我精進(今の自分を超える)」という建学の精神と、「自分の人生を生きる」という教育目標に深く結びついています。
田園調布学園の教育は、単なる知識の詰め込みや大学進学実績の追求ではありません。生徒一人ひとりが自分自身の「軸」を見つけ、比較や評価に惑わされることなく、生涯にわたって豊かに生きるための土台作りを、何よりも大切にしているのです。
最後に、この記事を読んでくださったあなたに問いかけたいと思います。 私たち自身の「成長」とは、本来、何と比べて測るべきなのでしょうか。そして、これからの時代を生きる子どもたちに、本当に必要な「力」とは何だと思いますか。