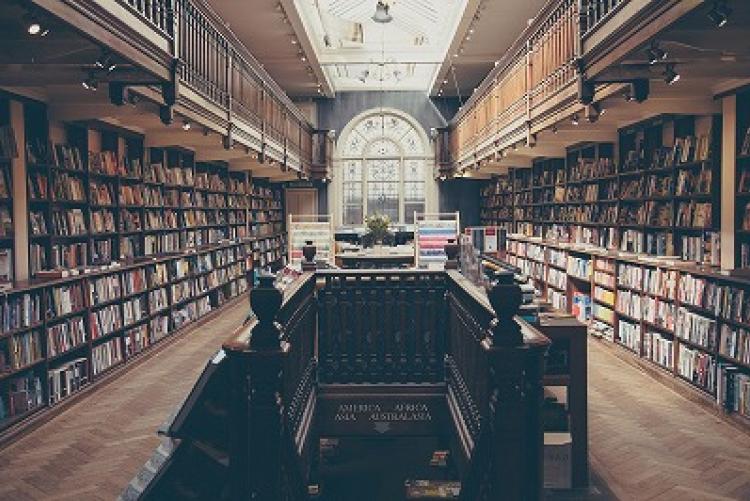「主体的な学び」——この言葉は、現代の教育現場で最も頻繁に聞かれるキーワードの一つです。しかし、その多くは「私がこれをやりたい」「自分の興味を追求したい」といった、個人の意欲や関心に焦点を当てたものとして語られてはいないでしょうか。もちろん、個人の探求心は学びの原動力として不可欠です。しかし、その「私」という主語に留まっている限り、学びは真の可能性を解き放つことはできません。
この「主体性」の概念を根底から覆し、学びを次のステージへと進化させている学校があります。それが、湘南白百合学園です。彼女たちの活動の根底には、「私」から「私たち」へと学びの主語を転換させる、一つの哲学的なコンセプトが流れています。
そのキーワードは、「We Turn」。
湘南白百合学園の教頭、水尾純子先生は、生徒たちがどのようにして校内の課題から社会全体の課題解決へと学びを昇華させているのか、その本質を解き明かしていきます。
1. 「We Turn」とは何か?
「We Turn(ウィー・ターン)」とは、一体どのような概念なのでしょうか。
この言葉は、もともと京都大学の出口康夫教授によって提唱された哲学的概念です。そして、私立学校研究家の本間勇人氏が湘南白百合学園の教育の革新性を分析する際に、その本質を捉える言葉として引用しました。
その意味は、極めてシンプルです。 「行動の主語が『私(I)』から『私たち(We)』へと転換すること」。
本間氏は、湘南白百合の教育がなぜ新しいのかを、こう解説しています。
「私が何々をしたいとか、そういうレベルから、主語がね、『私が』じゃなくて、『私たちは』に変わっていく、We Turnという一つのコンセプトを打ち立てているんです」
個人の興味から始まった学びが、いつしか仲間を、他者を、そして社会を巻き込み、「私たち」のプロジェクトへと進化していく。このダイナミックな転換こそが、未来を切り拓く教育の答えなのです。
2. 学びの第一歩:校内で芽生える「私たち」の創世記
この「私たち」という意識の育成は、講義室ではなく、むしろグラウンドのような場所から始まります。そこでは、日々の学校生活そのものが、集団で何かを創造するキャンバスとなるのです。「私の学校生活」が、ごく自然に「私たちの学校生活」へと転換していく、その創世記がここにあります。
体育大会:ルールさえも「私たち」で創る 湘南白百合の体育大会は、単に競技に参加するだけのイベントではありません。運営はもちろん、競技そのものまで生徒たちが企画・開発します。例えば、既存の「玉入れ」をひねり、妨害役を設けた「玉入れさせない」といったユニークな競技が生まれます。これは、個人の勝利や楽しみだけでなく、どうすれば学年を超えた全員が楽しめるか、という「私たち」の視点でイベント全体をデザインしているからこそ生まれる発想です。
スラックス制服の考案:個人の声が、姉妹校全体の未来を変える 「スラックス制服を導入したい」。一人の生徒の声から始まったこのプロジェクトは、3年という歳月をかけて大きな実を結びました。生徒たちは単に要望を出すだけでなく、デザインを考え、制服の工場まで見学に行き、試行錯誤を重ねました。セーラー服に合うよう裾を少し広げたマリンスタイルのデザインは、生徒たちの徹底的な探求の賜物です。これは単なる制服の選択肢追加の要望ではありませんでした。それは、「私たち」のアイデンティティを再定義するための数年がかりのプロジェクトであり、そのプロセスから生まれた知恵は非常に深く、彼女たちが創り上げたモデルは、スラックスを導入する際の公式モデルとして、全国の姉妹校で採用されることになったのです。
3. 境界を越える:「私たち」の輪を拡張する
校内で育まれた「私たち」という意識は、学校の垣根を軽々と越えていきます。湘南白百合の生徒たちだけだった「私たち」は、他校の生徒、大学、そして社会へと、その輪をダイナミックに拡張していくのです。
他校との連携:「初めましてのチーム」で挑む複雑な課題 湘南白百合の生徒たちは、本郷中学校・高等学校や聖光学院といった男子校など、異なる文化や背景を持つ他校の生徒たちと「初めましてのチーム」を組みます。そして、医療、防災、生成AIといった、答えのない複雑なテーマに共同で取り組みます。ここでは、性別も学校も異なるメンバーが、共通の課題に向き合う中で、ゼロから新たな「私たち」という共同体を形成していくプロセスそのものが、深い学びとなります。
北海道オホーツクでの探求活動:多様性の中から「私たち」の価値を見出す 夏休みには、東京農業大学や他校の生徒たちと共に北海道オホーツクへ赴きます。ここでのテーマは「美」。まず生徒たちは、デジタル画面の画素の拡大写真や、空の写真を逆さまにして宇宙に見立てるなど、多様な「美」の捉え方を共有。その後、オホーツクの自然素材と、トップノートやミドルノートといった香りの変化を計算しながら自分だけの日焼け止めクリームを作り、外見的な美を探求します。一方で、都会からの移住者の話を聞いた後には、「他の中高生が聞きに行きたいと思えるようなシンポジウムのタイトルを考える」という課題に挑戦。異なる価値観を持つ初対面のメンバーが、抽象的なテーマについて対話を重ね、一つのチーム=「私たち」として思考を深めていくのです。
4. 学びの完成形:社会と接続し、貢献する「私たち」
「We Turn」の最終段階は、学びが教室やプロジェクトの中だけで完結せず、具体的な社会貢献や課題解決のアクションへと繋がっていく点にあります。このとき、「私たち」の輪は、地域コミュニティや社会全体を包み込むまでに広がります。
防災マップの作成:学びを「自分ごと」から「地域ごと」へ 東北大学や聖光学院と連携した防災プログラムに参加した生徒は、学んだ知識を自分の中だけに留めませんでした。「この知識は、私たちが住む地域の人たちにも共有しなければならない」。その強い思いが、彼女を行動へと突き動かします。校内のクリエイティブスペースにある3Dプリンターを駆使し、自分たちの住む地域の浸水域や崖崩れの危険箇所が一目でわかる立体地図を作成。そして、地域の防災訓練に参加し、住民への啓蒙活動を行ったのです。これは、専門家から得たデータや情報(Data/Information)を、防災に関する知識(Knowledge)へと体系化し、最終的に地域社会のための具体的なツールを創造するという知恵(Wisdom)へと昇華させた、まさに「We Turn」の完成形です。
デフリンピックチームとの交流:社会のあり方を共に考える 障害を持つ人々への関心から自主的に勉強会を開いていた生徒たちの活動が、ポルトガルのデフリンピックチームを学校に招くという大きな交流に発展しました。この繋がりには物語があります。2020年東京五輪の際、藤沢市はポルトガルのホストタウンであり、当時小学生だった彼女たちが同国のオリンピックチームと交流していました。数年後、高校生になった同じ生徒たちが、今度はデフリンピックチームと再会したのです。言葉の壁を越え、ボッチャなどを通じて心を通わせる中で、生徒たちは「より良い社会とは何か」を当事者と共に考え、よりインクルーシブな社会を目指す「私たち」の一員としての自覚を育んでいます。
結び:未来を「共創」する生徒たちと、知恵(Wisdom)への道筋
湘南白百合学園の教育は、単なる知識の習得や個人のスキルアップを目指すものではありません。それは、「We Turn」という思想を軸に、生徒一人ひとりが多様な人々と関わりながら新しい「私たち」を形成し、社会に存在するリアルな課題に働きかける力を育む、壮大なプロセスです。
このプロセスは、本間氏が指摘する、生徒たちが「知恵」を身につける過程そのものです。彼女たちは、データ(Data)を集め、それを整理して情報(Information)に変え、体系化して知識(Knowledge)とし、最終的に社会のために応用する知恵(Wisdom)へと高める「DIKWピラミッド」のサイクルを、プロジェクトを通じて自然に実践しています。「We Turn」こそ、このピラミッドを駆け上がるための強力なエンジンなのです。
だからこそ、彼女たちは在学中から社会で「即戦力」となる本質的な力をその身に宿しています。彼女たちの姿は、これからの教育が目指すべき方向を明確に示しています。それは、孤立した「私」を育てるのではなく、他者と協働し、未来を「共創」できる「私たち」を育てる教育です。
水尾教頭先生にこのような環境を引き出す教員側の問いの設定について尋ねると、次のような答えが返ってきました。
「いや私、そんなにチャレンジングな問いかけをしているわけではなくて、逆にもう面白がってる人です。生徒たちが『こういうのはどうかな』って言った時に、『なんかそれすごい面白いね』と私がすごい感動していると、『じゃあもっとこういうのありかな』みたいにどんどん子どもたちは先に行ってしまうので、なんかそれを一緒に面白がりながら歩いていっているっていう感じです」
この「私たち」という主体性を持つ学びこそが、今の湘南白百合の生徒たちの力につながっており、現在の活動がそのまま未来に直結しているのです。この新しい教育のあり方こそが、今後、他の教育機関が見習うべき重要な点であるわけです。