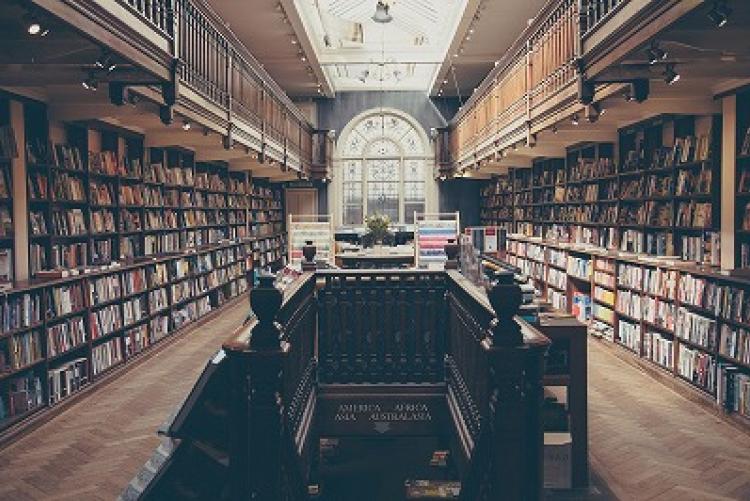1. はじめに
予測不可能な未来、いわゆる「VUCAの時代」を生きる子どもたちのために、本当に価値のある教育とは何か。多くの保護者が頭を悩ませるこの問いに、一つの私立学校が驚くべき答えを提示しています。芝国際中学校・高等学校の挑戦は、単に新しい科目を教えることではありません。それは、学校と生徒の関係性を根底から再定義し、「学校を生徒と共に創る」という、シンプルでありながらも革命的な試みです。芝国際の校長である吉野先生と入試広報部長の川上先生が、同校のユニークな哲学から得られる、最も示唆に富み、常識を覆す5つの視点から、これからの教育に求められる本質を紐解いていきます。
Takeaway 1: 「平和学習」の行き先はUSJ? 生徒がゼロから作り上げる修学旅行
芝国際では、文化祭、体育祭、そして修学旅行といった主要な学校行事が、すべて「0から生徒が作り上げる」ことを基本としています。学校側が用意したテンプレートは存在せず、生徒たちが企画、議論、プレゼンテーションを重ねて、すべてを決定していくのです。
その象徴的な例が、1期生の修学旅行です。学校側が提示したガイドラインは、たった一つのテーマ「平和」だけでした。生徒たちは議論を重ね、行き先を大阪に決定します。しかし、その計画の中で最も周囲を驚かせたのは、旅程に「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)での丸一日の滞在」が含まれていたことでした。
「平和」というテーマに対し、一見すると無関係に思えるこの選択。しかし、生徒たちはプレゼンテーションで力強くその論理を語りました。教員だけでなく、最終的には保護者の前でもプレゼンを行い、アンケートによる承認を勝ち取ったその主張とは、次のようなものでした。
平和のためには笑顔というものが絶対に欠かせない。で笑顔を生み出すって何なんだろうというところを掘り下げたい。
この主張は、単に楽しい場所に行きたいという短絡的な発想ではありません。「平和と笑顔の関係性」という独自の視点からテーマを再解釈し、エンターテイメントが持つ力を探究したいという知的な探究心に裏打ちされています。このプロセスは、企画力を養うだけでなく、自らの考えを論理的に構築し、最大のステークホルダーである保護者をも説得し、学びの真の当事者となる力を育んでいます。
Takeaway 2: 教員にAIを教える生徒たち。「学校を一緒に作る」という文化
この生徒への信頼は、学校行事だけに留まりません。芝国際の根幹をなす理念は、「生徒と一緒に学校を作っていく」という文化そのものです。この理念がどれほど徹底されているかを示す、まさに常識破りなエピソードがあります。
ある時、生徒たちが「芝国際の教員のAIに対する知識が十分ではない」と感じ、自らAIに関する研究会を企画したのです。驚くべきことに、彼らは自分たちでその分野の第一人者に連絡を取り、講師として招聘しました。そして、教員だけでなく、校長や理事長、理事までも参加者として招待したのです。
これは、生徒が単に知識を受け取る消費者ではなく、学校という共同体の重要なステークホルダー(利害関係者)であることを示しています。自分たちに必要なものを見極め、学校の方向性を能動的に形成する。この常識を覆すほどの生徒への信頼こそが、芝国際の活気の源泉となっているのです。
Takeaway 3: 「幸せ」の先へ。AI時代を生き抜く「ロゴス・パトス・エートス」という羅針盤
こうした生徒主体の活動を支えているのが、学校の明確な教育哲学です。芝国際が目指す究極のゴールは、生徒一人ひとりの「幸せ」ですが、その定義は非常に深く、多角的です。吉野明校長は、単なる精神的な幸福だけでなく、「ウェルビーイング(Well-being)」という概念を提示します。それは、「生命の健康」(肉体)、「生活の福祉」(社会)、そして「人生の幸福」(精神)という3つの側面が満たされた状態を指します。
そして、このウェルビーイングを実現するために、AI時代を見据えた人間ならではの能力を、古代ギリシャの弁論術に由来する3つの要素を羅針盤として育成します。
1. ロゴス (Logos): 論理・理屈
2. パトス (Pathos): 情熱・共感
3. エートス (Ethos): 人格・信頼性
AIが論理(ロゴス)の多くを完璧に代替できる時代において、人間に残された本質的な価値は、人の心を動かすパトスや、他者からの信頼を勝ち取るエートスにある、と同校は考えています。この哲学はカリキュラムにも反映されており、数学や語学で「ロゴス」を、芸術や文学で「パトス」を、そして他者と協働し説得する「探究」の授業を通じて「エートス」を磨き上げます。この揺るぎない哲学的基盤が、学校のすべての活動に一貫した「なぜ?」という問いへの力強い答えを与えています。
Takeaway 4: IBよりケンブリッジ。世界標準への現実的で賢い選択
その哲学は、グローバル教育の選択にも表れています。国際教育への関心が高い保護者にとって、同校の選択は非常に示唆に富んでいます。芝国際は国際コースを設置していますが、近年日本で知名度が高まっている国際バカロレア(IB)ではなく、「ケンブリッジ国際教育プログラム」の導入を進めています。
その理由は極めて現実的かつ戦略的です。IBは導入のための費用や教員研修の負担が大きく、日本の学習指導要領との両立が難しい側面があります。一方、100年以上の歴史を持つケンブリッジのプログラムは、日本の教育との「親和性」が非常に高いとされています。これにより、日本の教育課程の枠組みを維持しながら、世界中の大学への進学資格を得られる、よりスムーズな世界標準への道筋を描くことができるのです。
この選択は、単に有名なブランドを採用するのではなく、生徒と教員にとって何が最も実践的で効果的かを見極める、地に足のついた学校運営の姿勢を物語っています。
Takeaway 5: 「指導」から「支援」へ。生徒が自らを律する学校
そして、この生徒を信頼する姿勢は、日々の生活の根幹にも貫かれています。芝国際は、従来の「生徒指導」という考え方から、「生徒支援」へと大きく舵を切っています。この哲学的な転換は、学校のあり方を根本から変えるものです。
何か問題が起きた時、その焦点は「処罰」にはありません。代わりに、「なぜその事態が起きたのか」を生徒自身が探究し、自ら改善策を見出せるようにサポートすることに重きを置きます。ルールで縛り付けて従わせるのではなく、内的な動機づけと責任感を育むことを目指しているのです。
このアプローチの一環として、現在、生徒会が中心となり、生徒たちが自分たちの手で学校のルールを定める「生徒憲章(チャーター)」の作成に取り組んでいます。外部からの規則による統制ではなく、自らが定めた規範によって自らを律する。これからの社会で自律した個人として生きていくために不可欠な経験が、ここにはあります。
7. まとめ
芝国際は、完成された学校ではありません。むしろ、教育者と生徒がパートナーシップを組み、日々対話を重ねながら共に作り上げていく「発展途上」の学校です。しかし、その根底には、未来を見通す深い哲学と、生徒の可能性に対する揺るぎない信頼が存在します。彼らのユニークな実践は、これからの教育のあり方を考える上で、多くのヒントを与えてくれるはずです。
もし学校が、生徒を教えるだけでなく、本気で信頼し、任せる場所だとしたら、そこからどんな未来が生まれるのでしょうか?