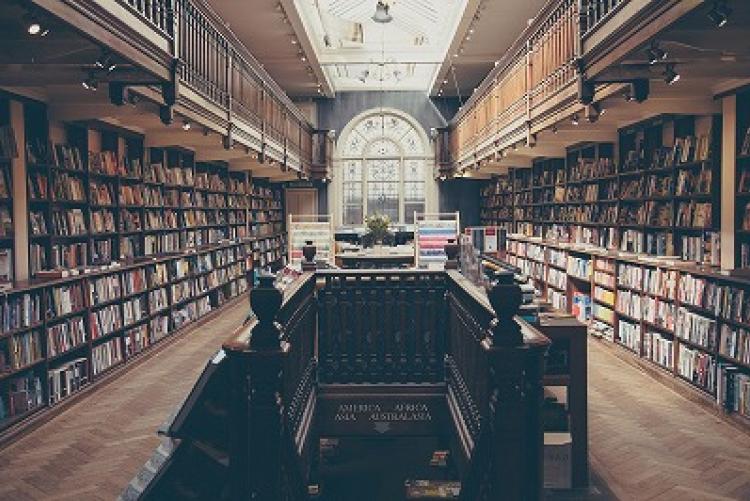ボーディングスクールでの生活 ①(Global Admission Webより)
GLICCでは、Global Admission Webというニュースレターを会員および購読者にお送りしています。
今回は過去の記事(2023年7月号)を紹介します。執筆者はGLICCチューターのY.K.くんです。
私は高校三年生の時にマサチューセッツ州アンドーバーにあるPhillips Academy Andoverに留学しました。ボーディングスクールの一例としてAndoverでの私の1日を簡単にご紹介したいと思います。
ボーディングスクールでは大多数の生徒が寮で生活をします。寮は学校内に位置することがほとんどのため教室には非常に短時間でたどり着けます。多くのボーディングスクールではそれぞれの生徒によって履修する授業が異なるため時間割は固定ではありません。1時間目がある日もあればそうでない日もあるといった感じです。私は基本は7:30に起きて準備をして食堂に行くというのが毎朝のルーティーンになっていました。仲良くなったルームメイトや寮の友達と待ち合わせをして食堂でパンケーキを頬張る朝はとても良い思い出です。