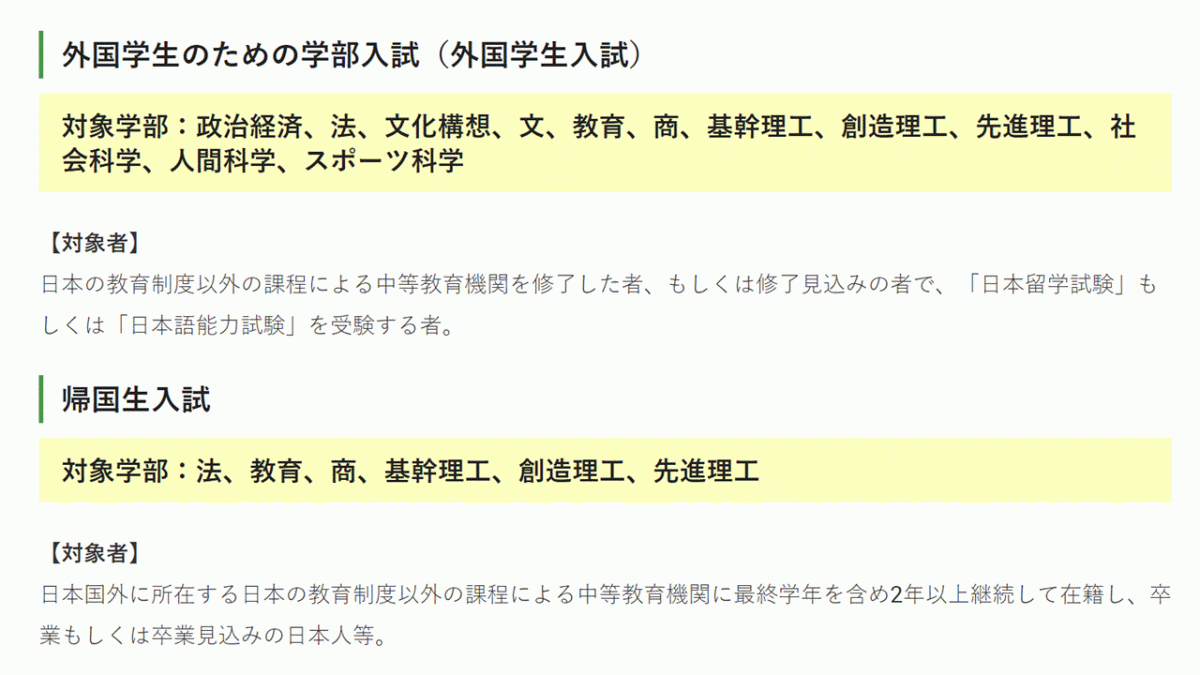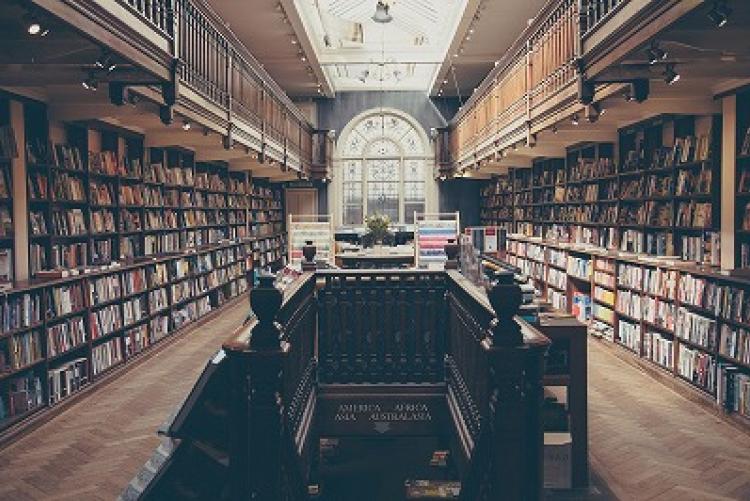慶應湘南藤沢高校 帰国生入試の変更点ーグローバルアドミッションの時代⑥
慶應湘南藤沢高等部では、一般入試の募集はしていませんが、全国枠入試と呼ばれる特別入試と帰国生入試を実施しています。昨年まではそれぞれ約20名と約30名だったのですが、2022年度入試では、内進生が増えることに伴い、それぞれ若干名、20名と募集人員が縮小します。
試験内容にも変更があります。全国枠入試では学力試験がなくなり、書類と面接による選考になります。帰国生入試でも英語の筆記試験はなくなり、英語資格を提出する形式に変わります。また、国語・数学も従来の各60分から各45分に短縮され、国語は「課題型小論文」の出題になるということです。英語資格については、TOEFL iBT 70点以上、またはIELTS 5.5以上、または実用英語技能検定試験(S-CBT/CBTを含む)準一級以上を取得していることが条件です。