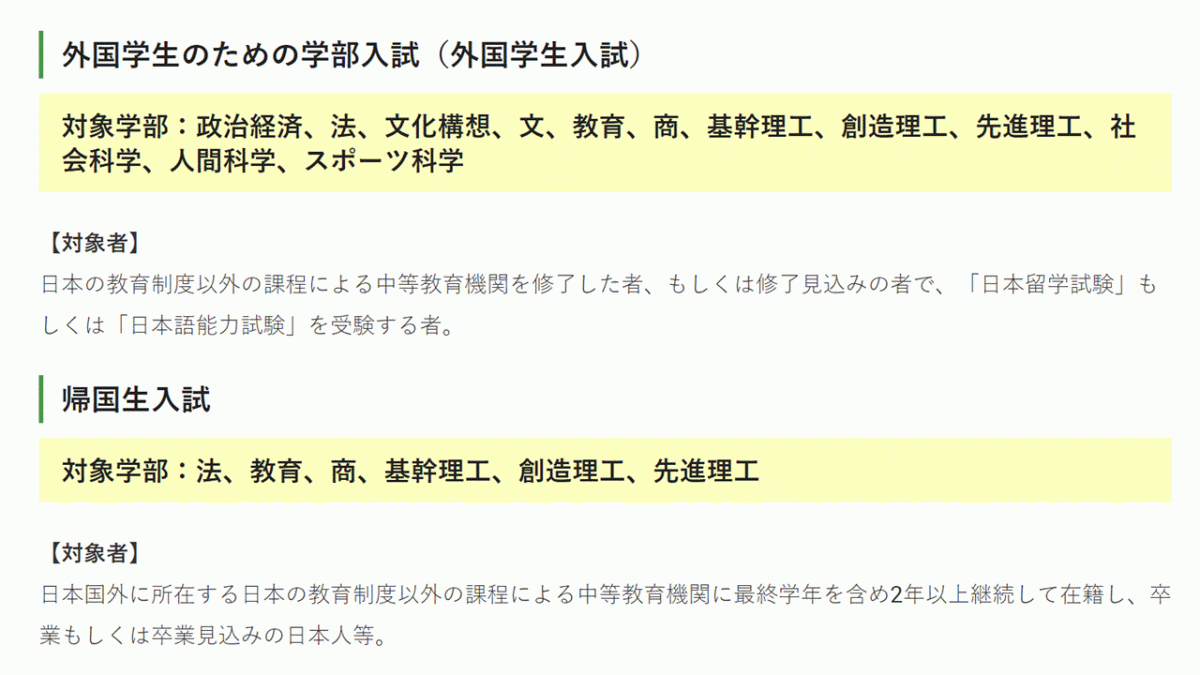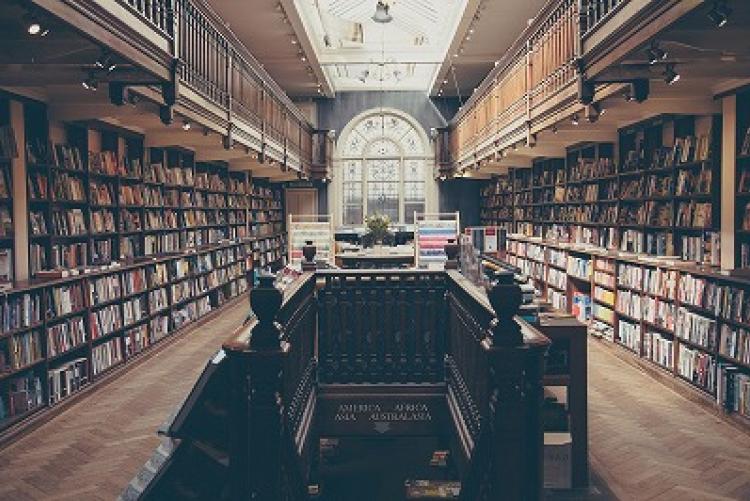IBDPのDual Routeに見る高大接続の意味―グローバルアドミッションの時代➂
今回のコロナパンデミックは受験制度のあり方を考える上でも大きな事件だったと思います。今春は試験制度の変更や授業形態の変化で国内の受験生は大きな影響を受けましたが、海外の受験生もまた大きな影響を受けました。帰国入試がオンライン入試などに変更されたケースもあれば、出入国の制限から帰国そのものを断念する家庭も少なくなかったようです。
なかでもIBDP(国際バカロレアのディプロマプログラム)を履修していた生徒は、昨年に引き続き、今年2021年5月の最終試験でも大きな影響を受けました。IBO(IB本部)はDual Routeといって、二つの選択肢を与えました。一つは、最終試験を行うルートで、もう一つは最終試験を行わないルートです。
このどちらの道を選択するかは、その国の感染状況や、学校で試験を行うリスクなどを考慮し、IBOと各国の教育省とが協議して決定したようです。結果的にはExam Route(最終試験を実施するルート)を選択した国の方が多数であるようですが、それでもPaper2が中止になったり、それによって内部評価(学校での成績)の比重が変わるなどの影響は少なからずありました。しかし、一番困惑しているのはNon-Exam Route(最終試験を実施しないルート)の方に置かれた学校の生徒たちです。